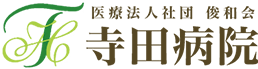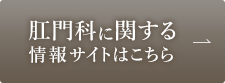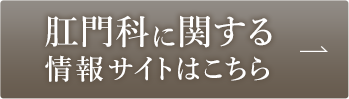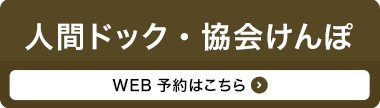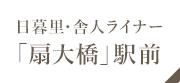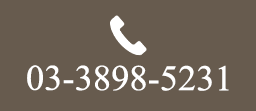潰瘍性大腸炎とは
クローン病と同じ「炎症性腸疾患」のうちの1つです。
大腸の粘膜に潰瘍やびらんができる炎症の病気です。炎症が初期の段階や軽度のうちは自覚症状も乏しく、もともと軟便がちな体質であり病気であるという認識がない人が多いですが、炎症が増悪してくると腹痛や下痢、血便という症状が出現してきます。
厚生労働省難治性炎症性腸管障害に関する調査研究班が行った疫学調査では、罹患者数が22万人以上と推察され、患者数の増加傾向が報告されています。実際に欧米化してきた食事による日本人の腸内細菌の変化やストレス社会などの環境の変化は関与しているでしょうが、そのほかに「大腸がん」を検査するための「大腸内視鏡検査」が、近年では内視鏡検査の発展から若い方でも下痢や、排便時に出血を認めている方で検査をする人が増えてきたため、ごく軽度の潰瘍性大腸炎でも発見される人が増えてきたのも増加の一因と考えられています。
潰瘍性大腸炎の発症のメカニズムは未だ明確な原因は分はっきりしていません。しかし遺伝的要因や免疫異常が関与し、睡眠不足、ストレスなどの心因的、体力的な負担の重なりが引き金となって発症するといわれています。原因に対する根治的な治療法は確立されておらず、症状に応じての対処療法が主体です。国の定める「特定疾病」に指定されており申請によって医療費の助成が受けられます。
発症年齢は10歳代後半から30歳代前半の若年者に好発します。治療は、根治は期待できず、炎症を抑制する対症療法が中心となります。症状が落ち着いている期間も、定期的な検査(採血、大腸内視鏡)を施行し、適切な治療を継続することで、状態が落ち着いている時期(寛解期)を長く保つことを目標にします。
潰瘍性大腸炎の症状と重症度(臨床的)
症状による重症度
初期段階では、症状に乏しく自覚症状はありません。炎症が増強してくると腹痛、下痢、血便が主症状です。特定疾病における特定医療費を申請する際は、特定の書類への医師の記入が必要になります。下記の症状に応じて軽症、中等症、重症に分類されます。

部位別分類
| 直腸型 | 直腸に限局する炎症 |
|---|---|
| 左大腸型 | 直腸から左半結腸(S状、下行結腸)に及ぶ炎症 |
| 全大腸型 | 盲腸まで直腸から全結腸にわたる炎症 |
潰瘍性大腸炎の部位別分類は上記の3つに分類され、直腸型:約22%、左大腸型:約27%、全大腸型:約38%です。
潰瘍性大腸炎の原因
潰瘍性大腸炎の原因はわかっていません。しかし、遺伝的因子と環境因子が複雑に絡み合い、何らかの免疫異常が、発症や炎症の持続に関与していると考えられています。
| 遺伝的因子 | いわゆる血縁者(父母、祖父母)に潰瘍性大腸炎の方がいると遺伝的に潰瘍性大腸炎の発症率がやや高いということが海外で報告されています。 |
|---|---|
| 環境因子 | 腸管の動きを管理しているのは自律神経です。自律神経は睡眠不足やストレスの蓄積で、動かなくなったり、動きすぎるようになったりしてしまいます。ですから自律神経のバランスが潰瘍性大腸炎の症状を悪化させやすいということになります。 |
潰瘍性大腸炎の検査と診断
 前述のように「潰瘍性大腸炎」を患っていても気づかず「少しお腹が弱い方だな」と思いながらも毎日の生活を送っている方も結構いるといます。
前述のように「潰瘍性大腸炎」を患っていても気づかず「少しお腹が弱い方だな」と思いながらも毎日の生活を送っている方も結構いるといます。
ただし、腹痛、下痢の持続や、排便時出血や血便を呈したときには「大腸検査」にて「潰瘍性大腸炎」を呈しているかどうかの確認が必要です。
逆に症状だけでは「過敏性腸症候群」から引き起こされる「便秘」や「下痢」によって「裂肛(切れ痔)」を呈している可能性もあり鑑別のために必要です。
「潰瘍性大腸炎」という診断は内視鏡にて荒れている粘膜部の生検(組織の一部をかじり取り、顕微鏡で観察)により明らかになります。長期間、大腸粘膜の炎症が持続した状態を続けると腸粘膜細胞の突然変異を来たしやすくがん化しやすいと言われています。症状の有無や増悪に関わらず、定期的に大腸カメラ検査を受けられることをお勧めします。当院では、高度な技術と知識をもった内視鏡専門医が検査を施行します。
また確定診断後は血液検査やCT検査にて他臓器に影響が出ていないかどうかも含めて全身チェックする機器も備えており、症状がひどい場合は入院施設も併設しているため安心です。
血液検査:貧血所見があるか、白血球やCRPなどの炎症反応が高くないかを調べます。細菌検査(便):細菌による胃腸炎との鑑別は便培養によって行います。
治療法
「潰瘍性大腸炎」の原因がわからない以上、原因に対する根本的な治療法は確立されていません。治療は症状に応じての対症療法が主体となります。
まずは現段階で炎症が活動期か?寛解期(落ち着いている)か?
前述の重症度分類において、どこに当てはまるか?
また炎症のある部位においても治療法や薬が違います。
寛解期であった方も、急に活動期に入ることがあり(再燃)治療を中断してしまうことは得策ではありませんので注意は必要です。
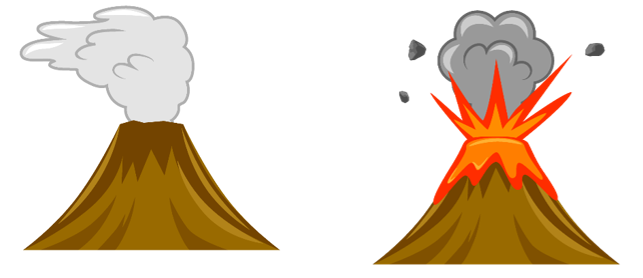
寛解期
潰瘍性大腸炎の寛解期は病気が治ったわけではありません。活動期から寛解に漕ぎつけた方が寛解の状態をなるべく維持できることを目的とした寛解維持療法が主体になります。基本的な生活習慣を意識し、薬の副作用が出ないなるべく最低限の治療を行います。
活動期 軽症の治療
5-アミノサリチル酸製剤(5-ASA剤)で粘膜の炎症を抑えます。5-ASA剤は炎症を鎮める効果があり、副作用も少なく、長期間に使用することができます。大腸がん発症の抑制にも繋がります。
5-ASA製剤は以下のものがあります。
- サラゾスルファピリジン(商品名:サラゾピリン®)
- メサラジン(商品名:ペンタサ®)
活動期 中等症の治療
5-ASA剤に加えて、ステロイド剤を併用します。しかしステロイド薬は炎症を抑える作用が強い一方、長期間の使用において副作用も現れてきてしまいます。(免疫抑制採用により易感染症、血糖値上昇、糖尿病の増悪、血圧の上昇、骨粗しょう症、顔のむくみなど)
活動期 重症の治療
内服ステロイド薬で症状が改善せずに重症になった場合は点滴のステロイド剤に切り替え、腸内の安静と栄養保持のため禁食として補液を行います。さらに抗TNF-α抗体製剤、カルシニューリン阻害薬などを併用します。抗TNF-α抗体製剤は関節リウマチの治療に広く使用されてきたもので炎症を引き起こす物質といわれる、サイトカインなどの作用を弱めます。代表的なものとして
インフリキシマブ製剤(レミケード)
アダリムマブ製剤(ヒュミラ)があげられます。
カルシニューリン阻害薬はいわゆる「免疫抑制剤」です。シクロスポリン(Cyclosporine A: CyA)とタクロリムス(Tacrolimus: Tac, FK506)が挙げられます。炎症に関わっている細胞(免疫細胞のひとつ T細胞など)の機能を抑えます。
脱水、電解質異常(特に低カリウム血症)、貧血、栄養障害などの改善のため全身管理が必要です。激症例は極めて予後不良であり、大学病院クラスの大きな病院にて消化器内科と外科の協力のもと緊急手術も念頭においての全身管理を強力に行う必要があります。
普段の生活での注意事項
寛解期であれば、それほど厳密な制限(運動・食事)はありません。しかし、自律神経の乱れは活動期への移行を誘発させてしまうため、十分な睡眠をとり、過度な疲労やストレスを溜めないといった、基本的な生活習慣は守る必要があります。
食事
バランスのよい栄養摂取を心がけること、暴飲暴食を避けることといった基本的な注意を行うことが求められます。
活動期は、炎症により腸の働き、動き的にも弱った状態ですから、消化の悪い食べもの、繊維質や脂肪の多い食品、香辛料などの刺激物を避け、優しい食事を心がけましょう。
潰瘍性大腸炎と大腸がん
潰瘍性大腸炎における長期にわたる慢性炎症は細胞の突然変異を引き起こしやすく、癌の発生の誘因となります。適切な治療の継続が大腸がんのリスクを減少させることがわかっているので、治療の中断はせず、定期的な受診や大腸内視鏡検査を心掛けましょう。